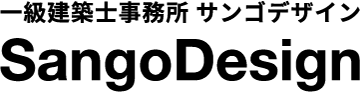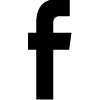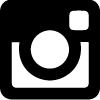[:en]
先日、僕たち夫婦の母校である武蔵野美術大学に行ってきました。建築学科の3年生の課題を対象に、OB・OG会である日月会が主催するコンペの審査員としてお呼ばれしました。

耐震改修をしてきれいになった芦原義信設計の4号館です。相変わらず、かっこいい建築でした。この建物を安易に壊さずに、補修して残したことは卒業生としてはとても嬉しいことです。

審査は教室や展示スペースに展示された学生の作品をひとつひとつ制作者の説明を聞きながらコメントや質問をして自分の中で採点していきます。審査時間は4時間の長丁場ですが、総数26作品をひとりづつ聞いていくと、結局ほとんど休憩なしの状態で時間切れになりました。久しぶりに感じる学生たちの熱気に圧倒されながらも、とても刺激的な時間でした。

学生の話を聞きながら、当たり前のことなんですが各学生が大事にしていること、価値観のようなものが、それぞれ異なっていて、順位を付けることが非常に難しかったです。また複数の課題が審査対象のため、設定自体が人によって違うこともまた悩ませる要因でした。

展示は屋外にまで及んでいました。原寸で制作した竹による構築物です。天気が良かったせいか、しばらく休憩がてらのんびりしていまいました。

各学生へのインタビュー終了後は、今年からの試みである公開審査協議に入ります。8人の審査員が、学生やOB・OG、講師や教授たちの見ている前で審査を議論し、各賞を決定します。各審査員それぞれに独自の価値基準があり、議論は徐々に白熱していきました。

聞いている学生たちも真剣です。この公開審査の試みは、細かい問題点もありましたが、学生にとってはとても良い試みだと感じました。自分の作品を審査員(第三者)にどのように捉えられたか、どこの部分が評価され、またどこの部分が評価されなかったかなど多くを学ぶことができる機会になったと思いました。

公開審査後は表彰式です。日月会賞の大賞である太陽賞を受賞した学生です。 審査中とは打って変わり暖かい雰囲気のにこやかな授賞式となりました。
日月会のホームページに8月上旬頃、審査員講評文が掲載されるそうです。僕もいま講評文を書いている所です。
日月会ホームページ:
http://www.nichigetsukai.com/
サンゴデザイン/鈴木竜太
[:ja]
先日、僕たち夫婦の母校である武蔵野美術大学に行ってきました。建築学科の3年生の課題を対象に、OB・OG会である日月会が主催するコンペの審査員としてお呼ばれしました。

耐震改修をしてきれいになった芦原義信設計の4号館です。相変わらず、かっこいい建築でした。この建物を安易に壊さずに、補修して残したことは卒業生としてはとても嬉しいことです。

審査は教室や展示スペースに展示された学生の作品をひとつひとつ制作者の説明を聞きながらコメントや質問をして自分の中で採点していきます。審査時間は4時間の長丁場ですが、総数26作品をひとりづつ聞いていくと、結局ほとんど休憩なしの状態で時間切れになりました。久しぶりに感じる学生たちの熱気に圧倒されながらも、とても刺激的な時間でした。

学生の話を聞きながら、当たり前のことなんですが各学生が大事にしていること、価値観のようなものが、それぞれ異なっていて、順位を付けることが非常に難しかったです。また複数の課題が審査対象のため、設定自体が人によって違うこともまた悩ませる要因でした。

展示は屋外にまで及んでいました。原寸で制作した竹による構築物です。天気が良かったせいか、しばらく休憩がてらのんびりしていまいました。

各学生へのインタビュー終了後は、今年からの試みである公開審査協議に入ります。8人の審査員が、学生やOB・OG、講師や教授たちの見ている前で審査を議論し、各賞を決定します。各審査員それぞれに独自の価値基準があり、議論は徐々に白熱していきました。

聞いている学生たちも真剣です。この公開審査の試みは、細かい問題点もありましたが、学生にとってはとても良い試みだと感じました。自分の作品を審査員(第三者)にどのように捉えられたか、どこの部分が評価され、またどこの部分が評価されなかったかなど多くを学ぶことができる機会になったと思いました。

公開審査後は表彰式です。日月会賞の大賞である太陽賞を受賞した学生です。 審査中とは打って変わり暖かい雰囲気のにこやかな授賞式となりました。
日月会のホームページに8月上旬頃、審査員講評文が掲載されるそうです。僕もいま講評文を書いている所です。
日月会ホームページ:
http://www.nichigetsukai.com/
サンゴデザイン/鈴木竜太
[:]